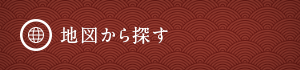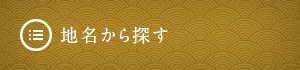住吉神社
神社のご案内
【延喜式神名帳】
筑前國那珂郡 住吉神社(すみよしのかみのやしろ)三座〔並名神大〕
- 神社名:住吉神社
- 神社名カナ:スミヨシジンジャ
- 鎮座地:〒812-0018 福岡市博多区住吉3-1-51(地図はこちら)
- URL:http://chikuzen-sumiyoshi.or.jp
御祭神
住吉五所大神
底筒男神(主祭神・そこつつのをのみこと)
中筒男神(主祭神・なかつつのをのみこと)
表筒男神(主祭神・うわつつのをのみこと)
天照皇大神(相殿神・あまてらすおおみかみ)
神功皇后 (相殿神・じんぐうこうごう)
由緒
住吉三神は遠い神代の昔に伊弉諾大神(いざなぎのおおかみ)が筑紫の日向の橘の小戸の
阿波伎原でミソギハラへ(禊祓)をされた時に、志賀海神社の御祭神・ワタツミ三神と警
固神社の御祭神・直毘の神と共に御出現になりました。したがって当社の御鎮座は遠い遠
い神代のことで、年代を定めることは出来ませんが、全国的にも九州でも最も古いお宮様
の一つです。住吉大神をお祀りする神社が全国に二千百二十九社ありますが、当社は住吉
の最初の神社で、古書にも当社のことを「住吉本社」「日本第一住吉宮」などと記されて
おります。
また、平安時代に全国各地に「一の宮」が定められましたが、当社は筑前の一の宮として
朝野の厚い崇敬を受けました。
約千八百年前、神功皇后の三韓への御渡航に際し、住吉大神の荒魂(あらみたま)は水軍
をお導きになり、和魂(にぎみたま)は胎中天皇と申し上げた応神天皇の玉体をお守りに
なり、刃(やいば)を用いずして御帰還遊ばすことが出来ました。よって皇后は住吉三神の
御神徳を厚く敬仰感謝され、新羅の都に国の鎮護として住吉大神をお祀りになり、また摂
津(大阪)、長門(山口)、壱岐に住吉神社を御創建になりました。住吉大神のご神徳は
、その御出現の由来に拝しますように、「ミソギハラへ」の御霊徳によってわれわれに心
身の清浄を保たしめ給い、そしてそれにより生ずる「開運と光明」をお恵みになるのであ
ります。更に、応神天皇の御代から国運大いに開けたこともあり、住吉大神は、文教、殖
産、興業、開運、安産、予言の神として信仰されております。
またツツノオ(筒男)のツツには星の意味があると言われ、筒男三神は航海安全、船舶守
護にその神威をあらされ、海運・漁業者の崇敬が極めて厚く「住吉丸」と名づけた船の多
いのもそのためであります。
このように御神徳が広大でありますので、当社への朝廷の御崇敬は特に篤く、神功皇后の
勅祭(十月十三日の例祭の起源)に始まり、聖武、清和、陽成、後一条、鳥羽、後花園の
各天皇が奉幣あらせられ大正天皇は三度、昭和天皇は五度の奉幣がありました。
また当社は諸武将の崇敬も厚く、楠正成、源頼朝、足利尊氏は祈願文、寄進状を寄せ、一
時は自国・他国を合わせ神領三千余町(ha)歩、神人三百余人に及んだと伝えられます
。江戸時代に入っては、黒田藩祖長政以来歴代藩主の崇敬は殊に篤いものがありました。
「由緒書」より
アクセス
【JR博多駅・地下鉄博多駅より】
徒歩10分